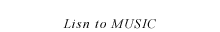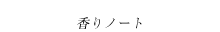桜の花の香り香りの向こうにある文化を知ること
2016.03.24
春の到来
桜の便りが届く季節。植物たちの芽吹きのエネルギーと匂いが鼻をかすめる。春の到来。今年の桜はどこへ見に行こう、そんな声も聞こえてくる。満開の景色はどこも圧巻。桜は咲いて散る姿が美しく、梅は香りが美しいなどといわれるが、ふと、この花の季節、桜の香りを知りたくなって香り探しの旅に出た。

京都の桜
京都に数多い桜の名所。円山公園の夜桜、疎水沿いのソメイヨシノ、遅めの花には御室仁和寺もいいだろう。国内外の人々が楽しみにしている桜。そんな桜を守り、調査し育てている人がいる。“桜守(さくらもり)” そう呼ばれるのは、植藤造園16代目当主、佐野藤右衛門さん。昭和3年生まれ、造園や桜の仕事で日本各地や海外を訪れ、桜にまつわる著書も多い。3月中旬、京都は嵯峨野にある庭園を訪ねた。園内では早咲きの花が咲き始め、数え切れないほどの蕾が開花の時を待っている。藤右衛門さんがさっそく花の香りについて話してくださった。
自然と暮らす
「芳香性の植物、代表的なものが梅やな。なぜ梅がいい匂いを出すかというと、寒い時に咲くから……じゃぁまずは “住”の話からはじめようか。昔の日本家屋では、雪隠(せっちん/お手洗いのこと)と風呂、台所、水回りは母屋から離れていた。今は全部家の中にあるけれども、昔はきちっと分かれていたんや。冬の寒い季節、雪隠から出ると梅の香りがする。そんな造りやったんやな。そしてその果実は梅干しにする。果実を作るためには昆虫や鳥が来てくれないといけない。けれども、寒い時期には虫も鳥も少ない。だから香りで誘っていた。その香りを、水回りの匂いを消すために上手に利用していたんやな。でも、桜が咲く季節には、もう春でたくさん昆虫もいる。だからあまり香りはないんやな」。暮らしと植物の香り。思いがけずに広がった香りの話しに引き込まれる。
「桜にあまり香りはないとはいっても、樹液には色々な成分が含まれている。それを上手に使ったのが染め。他にも山桜を面皮(めんかわ)にしたり、灰にして釉薬にしたり。最後は土に帰す。昔の暮らしでは植物が持っているものをうまく使っていた。それが今では技術的に香りを抽出したり……それは桜の本当の香りではないと思う。自然界のものを使うとなれば、細かいところまで知らないと本当の意味では使えない」。趣味でなさるという焼物。桜の灰で作られた釉薬。どんな種類の木からどんな色が生まれるのか、そこには色とりどりの器が並んでいた。

桜の香り
庭園では「十六夜(いざよい)」という品種の桜が花開いていた。藤右衛門さん曰く、青臭いという香り。青臭いとは一体どんなものなのか。差し出してくださったそのひと枝に、植物がもつ香りの素晴らしさを知ることとなる。透明感、瑞々しさ、甘さ、言葉では表現しきれないような、初めて知る香りだったのだ。香りに酔うような、クリアで甘やかな香り。思わず出た「いい匂い」という言葉。「桜の香り。どの桜をイメージするのかが大切や。本来の京都の桜、山桜をイメージしないといけない。とくに赤芽の山桜がいいな。オオシマザクラは葉の香りがいいけど、花はあまり咲かないんや」。楽しそうに話してくださる笑顔が印象的だ。

香りの文化
藤右衛門さんは香りの文化にも造詣が深い。インセンスをたく間の15分、こんなお話をしてくださった。「煙の立ち方で、昔の日本人は天気もわかった。湿度もわかる。湿度が高ければ燃えるのにも時間がかかる。遊郭でもお線香で時間をはかったり。そんなこともあったんやで。煙も“立つ”といったり、“なびく”といったり。香りのことで、言葉の遊びや文化までを知れる。それを今の人は忘れている。お香1本がものすごく奥深い」。俺の雑学やから学説とは違うで、と笑いながら話してくださる。
「1本のお香には香りの歴史の重みがある。仏教のことを含めばもっと長い。燃えるという現象だけを見ていてはいけないな。その背景を知り、それを時代に合わせてまとめることが大切なんや。香りをたくと、多くの人が同じ環境の中に入れる。香をたきこむという言葉、本当にいい言葉やと思う」。日本人が培ってきた文化。革新の裏には基本をしっかりと積む。そして、遊ぶことが大切と藤右衛門さん。「すべて地球上にあるものの命をもらって作らせてもらっている、それが最後に人間のためにはかない煙になっていくんやな」。

花が咲くということは、1年間の成果が出るということ。桜守にとって満開の時は、ほっと一息つくときだという。桜を守り、育てる人との出会いは、香りを知り花を愛でるだけにとどまらず、日本の文化を見直す機会となった。桜を知ろうとした今、私たちの「文化」や「暮らし」の本質をあらためて問われているような気がした。