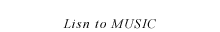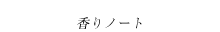暮らしの素。土に春を感じる土を巡る旅
2015.03.16
雨が、はりつめた空気を緩ませる。いよいよ本格的な春がやってくるのだ。慈しみの雨をいっぱいすいこんだ土は、植物を、虫たちを、生けるもの全てを目覚めさせる。足もとへ意識を向けて思うのは、土は、人の命を養う作物を育み、暮らしに寄り添う器の素となるということだ。春の訪れの匂いをたどって、大地へ足を踏み出す。季節の移ろいのにおい


命をはぐくむ土、対話する農
京都市内から北へ、北山杉の姿美しい京北には、まだ冬の名残があった。10月の終わりには霜が降り、冬の間は雪に覆われるというこの地で、土にこだわった野菜づくりをはじめて3年目の市原正隆さん。彼の作る野菜はさっぱりとした味わいと軽やかな香りが特徴で、彼の野菜を楽しみに待つ人が多いという。
「人は自然の調整役だと思うんです。土がもともと持つ生命力を活性化させてあげることで、そこで育つ作物が元気になることが自然の流れだと思います」。籾殻やヌカ、木材チップなど植物性のものを使い、土に住む微生物の活動を活発にさせて土づくりをする。野菜が育つための土壌を活性化させることが、何よりの肥やし。活力を循環させるのだ。
「手をかけて目をかけ、面倒をみることで土は生き生きする。手触りや匂いで、その土が生きていることを感じられるんですよ」そう話しながら、土の匂いを確かめる正隆さんの顔がほころんだ。籾殻の下から顔を出した土には菌糸がついていて、確かに発酵が進んでいた。冬のあいだ目をつむるように静かだった土は、静かに息をしてその活力をためていたのだ。生きている香りがする。甘みのあるような、優しい雨を存分にすいこんだ土の匂いがした。

つかう美しさ、暮らしのなかの土
一方、器の素となる土を訪ね、兵庫・篠山へ向かう。
篠山城跡には早春の日が差し、そのすぐ北部にある山麓の集落では、雨や雪がこぼれる。雲が一直線に天気を分ける不思議な光景のただなかにある工房を訪ねた。丹波焼は日本六古窯のひとつ。「日常雑器を作り続けてきた丹波焼の歴史と、暮らしと結びついて使われてきた器の美しさをもっと知ってほしいと思ったのです」。柴田雅章さんは大学卒業後、師のもとで焼物を学び、篠山のこの地で作陶に励んで40年、丹波焼の器を作り続けている。
柴田さんは、丹波で江戸時代中頃からずっと同じ場所で取れる土を水で漉したあと、じっくり1年かけて熟成させて作陶に用いる粘土をつくる。クリーム状の粘土を「荒もみ」で硬さを調整し、「菊もみ」(手で練り上げるとき菊の花のようになることから)でさらに練り上げて空気を抜く。そしてろくろでの成形など、ひととおり見せていただく傍らにあった薪ストーブに目がとまった。薪に使用するカシやナラなど数種類の灰が、釉薬に使うための材料になるというのだ。工房の外にはこの地に生きると決めた40年前からある登り窯。何十回という焼入れの歴史が、窯の内側の光沢と、膨張と収縮を繰り返して歪んだその様から伝わってくる。土や植物の灰からできる釉薬など自然の産物からなる器を焼くには、薪からの炎がいい。
「生活の中で使う器だから、暮らしの中から生みだしたい。そのために自然なサイクルで生活して、四季のうつろいを感じながら生きています」。


土が紡ぐ未来
今年、四十路を迎える登り窯のすぐ隣りにもう一機、窯が建つという。後を継ぐ貴澄さんの窯だ。
そして“使ってこそ”の陶の魅力を誰よりも知る長女の咲美さんは、篠山城の近くで茶房を営み、食や茶を通じて茶器や器のよさを伝えている。咲美さんの2歳になるお嬢さんは、陶器の器でご飯を食べる。「こんなに小さな子でも「だいじだいじ」と言って聞かせると、乱暴に使ったり割ったりすることはないんですよ。使うことで感じとってるんでしょうね」。

母なる大地は、私たちが口にする野菜を育て、手にする器に姿をかえ暮らしに寄り添う。形が整った均一なものが量産されるいま、一つひとつ違う顔を持った器や野菜たちは私たちに、どう生きるか、自然のもとに暮らすとはということを再認識させてくれた。
力を蓄えた土の香りを確かに感じながら、季節は春へとうつりゆく。
SPECIAL THANKS
陶芸家 柴田雅章さん
柴田さんの器が買える場所、器でお茶が飲めるカフェ