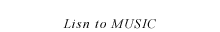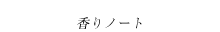香る魚のはなし鮎が生み出す旨味と香り
2016.05.19
香魚の季節
秋に川で生まれた稚魚は、冬を大海原で過ごし、春にまた川に遡上する。解禁日を過ぎれば愛好家たちが清流で釣りを楽しみ、簗(やな)漁や鵜飼といった漁法も有名な夏の魚、鮎。塩焼きか、甘露煮か、食で旬も楽しみたい。キュウリウオ目に分類される鮎だが、体にはスイカやキュウリのような青い香りをまとっており“香魚”の異名をもつ。香りにまつわる“魚”という気になる存在。そんな魚にまつわる香り探しは、西の地へ。

鮎からつくられる醤油
雄大な流れの筑後川。阿蘇山を水源に有明海に注ぐこの川の上流では鮎漁や養殖が盛んだ。大分県日田市は、筑後川の上流、三隈川が流れる水郷の地。水が豊かなこの地では、酒や味噌、醤油の醸造元が古くから栄え、今でも老舗が残る。日田駅から歩いて10分ほど。白壁の趣きある建物が見えてくる。この地に暖簾を掲げ100余年、味噌と醤油の醸造元、原次郎左衛門蔵を訪ねた。鮎魚醤(あゆぎょしょう)なるものを作っているというのだ。魚醤と聞いて思い浮かぶのは、ハタハタから作られる“しょっつる”や、イワシから作られる“ナンプラー”だが、鮎魚醤とは初耳だ。香魚から作られる醤油とはいったいどんなものなのだろうか。
匂いのない魚醤
「一般的な魚醤には独特の匂いがあるんですが、鮎魚醤にはその臭みが不思議とないんです。それが鮎魚醤の一番の特徴。食材の旨味を引き立てるような役割をしてくれるんですよ。」そう教えてくださったのは、4代目原次郎左衛門の正幸さん。「この辺りでは鮎の養殖が盛んで、その鮎を一度に冷凍して保存するんですね。でもその時に、どうしても傷ついたり、小さかったり、規格外のものが出る。それをうまく魚醤にできないかという依頼をいただいて。魚醤は匂いが強いので悩んだんですが、酵素研究の方と出会ったり、大分県あげてのプロジェクトになったりと、段々と大きな取組みとなりました」。2000年にスタートした取組み。研究や試作から半年で“匂いのない魚醤”に辿り着いたという。はじめは廃棄になってしまう鮎を使っての取組みだったが、徐々に大規模な商品開発へと進み、川魚を食べることが減ってきている現在では、使っていない生簀(いけす)を有効利用しての取組みとなっているという。

素材の旨味と香りを引き出す優れもの
「魚醤特有の臭みがない分、逆に一般的な魚醤と同じような使い方はできません。イタリアでは古代ローマ時代に魚醤が発祥したといわれているので、イタリアのシェフへも営業をはじめました。少しずつですが、料理人の方が気に入ってくださり、料理の引き立て役として使っていただいています」。独特の臭みがない、という鮎魚醤は、一般的な魚醤とは販路を別にしているようだ。匂いはなく旨味だけがある。そして不思議なことに、他の食材の嫌な匂いもうまい具合に消してくれるという優れものらしい。雑味がなくシンプルな味わいの鮎魚醤を少し使うことで、ほかの素材の嫌な味や匂いは消え、旨味や香りが引き立てられる。「カルパッチョや魚のあら炊きなんかに使うととても良く合います。より上品で良い味になりますね」。
いったいどんな味わいなのか、一口いただく。臭みは全くない。濃すぎず、薄すぎず、コクのある味わいが口の中に残る。それが全く嫌みではないのだ。香りをもつ魚が姿をかえ、その香りを旨味にかえていることがわかる。料理人の舌をうならせる味なのだという。香魚をめぐる旅は、世界へと広がっていった日田の味との出会いとなった。

次なる醤へ
穀物から作られる醤油、魚から作られる魚醤、肉類が原料の肉醤、そして海藻や野菜が材料となる草醤、そして未醤(味噌のこと)。平安時代の書物にも記録が残っているというこの5種の醤(ひしお)。原次郎左衛門蔵では草醤以外の4種をすでに製造しているが、この夏に5種目の草醤がいよいよできあがるという。「味と香り、品質、自信を持って世界一といえます。大切に育てていきたい逸品ですね」。
香りをまとう魚が主役となる調味料。このほんの少しの隠し味が、世界中の料理に深い味わいを添える日。それはもうすぐそこまできているかもしれない。
SPECIAL THANKS