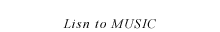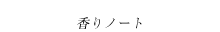数百年後にまた職人の魂と伝統をつなぐ鬼瓦
2021.01.25
見上げた先に
なんだか急に散歩がしたくなって外に出た。あてどなくしばらく歩く。この時期の冷たい風が意外と心地よくって、たまには悪くないなと思いながらふと立ち止まり目をつぶってみた。冬晴れの空気を胸いっぱいに吸い込んで目を開けると、艶やかに光るいぶし瓦の屋根。その端にある鬼瓦にふと目が留まる。もうすぐ節分。豆で払われてしまう鬼もいるけれど、じっとそこにいて人の世を見守る鬼もいる。そんな鬼に出会う旅。
鬼の生まれるところ

かつて瓦産業が盛んだった滋賀県大津市松本。そこから北へ、比叡山延暦寺の門前町として栄えた坂本の地で、四代にわたり鬼瓦をつくり続ける工房がある。案内してくださったのは美濃邉 恭平さん。力強い眼差しが印象的な、温かい職人さんだ。

「まず鬼瓦といえば鬼面瓦(きめんがわら)をイメージすると思いますが、ほかにもいろんな種類があるんですよ」と美濃邉さん。雲や立浪、巻物の形を模したものも鬼瓦と呼ばれるそう。その繊細な造形は、ひとつひとつ手作業で生み出される。建物の特色に重ねた人々の願いが詰まった、職人の技が光る代物だ。鬼瓦を作る職人は特に鬼師(おにし)と呼ばれ、一般的な屋根瓦の職人とは区別されてきた。
美濃邉さんの仕事の多くは、数百年前の鬼師が作った鬼瓦の復元や修復だそうで「見本通りにする仕事」と話す。よく観察し、手で触れることで、先人がそこに込めた想いを汲み取り、形を再現していく。機械的にたくさんの商品が生産されていく世の中で、手で作ることに意味があるのだと美濃邉さんは言う。「人間の手でつくる、ということが技術になる。それが伝統になる」 技術を瓦にのせて守り伝えていく、そんな現場を見せていただいた。
優しい香りから
工房に足を踏み入れると、かすかにふわりと香る乾いた土の匂い。瓦は粘土を焼いて作られる。 鬼瓦に適した三州の三河土に少しずつ水を加えながら、土練機(どれんき)と呼ばれる機械を使って丁寧に練り上げる。機械とはいっても混ぜるだけのシンプルな仕組み。大切なのは粘土の感触を手で何度も確かめながら、水分の量や土の混ざり具合をつぶさに観察すること。土練りの細かい工程一つ一つが瓦の出来に影響するから、経験と感覚が頼りの気が抜けない大切な工程だ。

練り上がった粘土を様々な厚さの板状にする。これをはり合わせて成形し、鬼瓦ができることから、鬼師は鬼板師(おにいたし)とも呼ばれる。鬼師の間ではちょっと縮めて互いを「おにたし」と呼び合うのだそう。雰囲気が柔らかくなった呼び名に、普段は鋭い眼差しの職人たちが集まる姿を想像して思わず笑顔になった。
粘土の板に触れると冷たくて、ピタッと指に吸い付く。角がピンと立った見た目から想像するよりずっと柔らかく、弾力も感じられた。この状態の粘土板を鬼師は熟練の技で “鬼” に変えていく。使い慣れた手作りの道具はよく手に馴染み、まるで身体の一部かのように繊細な力加減を汲み取って土を削っていく。

瓦と向き合う
成形後、乾燥させる工程はとても重要。少しでも水分が残っていると焼く時に割れてしまう。かといって慌てて乾かしても焼く前にひび割れてしまう。目には見えない水の動きを想像しながら、大きな鬼瓦をひっくり返したり、部分的に覆ったりして、全体が同じ乾き具合になるよう調節する。決して派手ではないが、時間をかけて行われるとても大切な工程だ。 まだ粘土が水分を含み黄味がかった“アオい”状態から、完全に水分が抜け、焼くことができる “白地(しらじ)” の状態になる過程で、その大きさは8%も締まるらしい。さらに焼くときにも5%小さくなる。最初に形作るときは、その分も計算して大きく作る。

土は、乾燥とともに質感が変わっていく。アオい鬼瓦は、板の時の柔らかさと弾力はないけれど、全体にしっとりと肌に馴染むような触感がまだ残っていた。白地は、よりはっきりと表面の具合を伝えてくれる。磨かれた部分は優しくてつるつるとなめらか、磨かれていない部分はざりざりとした粒子の存在がしっかりと感じられる。なんだか人の成長にも似ている。

次に白地は窯でじっくり焼かれる。最後に温度を下げ、煙を入れて燻す。そうして中まで炭化させることで、強さと洗練された上品な艶を持つ“いぶし銀”の鬼瓦が生まれるのだ。 そんな窯焚きは鬼師の正念場。時には手塩にかけて育ててきた鬼瓦が、一瞬にして駄目になってしまうこともあるという。「毎回窯が違う」笑みを浮かべて冗談も言いながら話す美濃邉さんの表情も、窯のことになると自然と鋭さを帯びていた。個々の大きさや細工の違いで変わる熱の伝わり方を考え、窯の中の配置を変える。いくら神経を尖らせていても、見えない窯中の炎の流れや細かい温度を調整するのは至難だ。火を入れてから36時間、1000℃以上にもなる窯を静かに見守り、焼いていく。 「ここまで愛情をかけてたものが、窯を開けてみて生きてたらええけど、死んでいる時もある」と美濃邉さんは静かに話す。鬼瓦一つ一つを我が子のように想う、鬼師としての熱意と誇りをその言葉から強く感じた。

生かすために生きる
優しい香りのする土からつくられる、硬くひんやりとした力強い鬼瓦。長い時間をかけて細かなところまで魂を込めて丁寧につくられていることを知った。屋根に上げられれば細部までは見えないのに、何故ここまで手間をかけるのか。「屋根葺き職人さんに見て欲しい。鬼師がここまで丁寧につくりよったんやから、これを綺麗におさめたろって。つくった瓦を最後棟にあげて葺いてもらうのは葺師さん。ええ仕事してもらうために、鬼師は仕事をする」葺師さんがいい仕事をすれば、いい屋根が出来上がり建物を長く守ってくれる。人の心を動かすことで人を守り、また長く継がれていく鬼瓦。それが美濃邉さんの考える“良い鬼瓦”だ。

「この令和の職人はええ腕しとるな」何百年後かのそんな言葉のため、生きている間はずっと気が抜けないと美濃邉さんは話す。 時代の流れとともに人の暮らしは変わっていき、文化や伝統を継ぐというのは大変かもしれないけれど「ものづくりに誇りを持っていれば、まだまだ日本も捨てたもんじゃない」と話す美濃邉さん。 「まあちょっと上を向いてもろうたら」そんな美濃邉さんの言葉と優しい目元を思い出しながら、今日も散歩に出かけてみる。