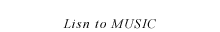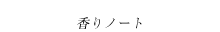ぬくもりの香り地域に伝わる種のはなし
2014.11.15
暮らしに根付くあずき
11月7日は立冬。冬支度を始める日だ。
西日本では、亥の子の日(11月の一番初めの亥の日)に炉開きをする風習があり、こたつなどを出したり、囲炉裏に火を入れる。お茶の世界でも炉がきられ冬のお手前が始まるという。茶事に馴染みがあるなしに関わらず、匠の手により表現された季節の和菓子の美しさには目を奪われる。そして、その柔らかで甘やかな姿にホッとしてしまう。これは日本人が大事にしている思いやり、もてなしの心を感じるからなのかもしれない。そして和菓子はもとより、お餅になくてはならい「あずき」に、我々は親しみを感じているのではないだろうか。お彼岸におはぎを食べ、祭りや祝いごとにはあずきがたっぷり入った赤飯を食す。あずきの赤色が邪気を払うとされ、いにしえより私たちの暮らしと密接に結びついている。

その土地の種を守り伝える
山間を縫って進む電車に乗って、あずきの在来種を守り育てる小さな集落を訪ねた。あずきがどんな花を咲かせ、どんな風に実をつけるのか知る人は少ないだろう。小さな黄色い花をつけ、青々としたさやをたくさん実らせる小豆の苗木をこの旅で初めて目にした。小さな苗木から、あの見慣れたあずきの姿を想像することはまだむずかしい。
在来種とは、ある地域で長年伝統的に育てられ、守られてきた品種のこと。種から種へ、受け継がれるもの。柳田隆雄さんの育てる「黒さや大納言小豆」は、そんな在来種を復活させたものだ。地域で大切にされていた在来種で作物を栽培していた“あたり前”は、効率性や生産性の訴求により激減した。


丹波の里で毎年、丹誠込めて育てられたあずきの種を、また来年も自分たちの手で育てる。連作によって種が弱くならないように毎年同じ畑で育てるのではなく、種を交換して別の畑で育てる。すると、同じ種で育てても不思議と味に畑ごとの個性が出てくると奥さんの明子さんが教えてくださった。もちろん育たない種もあるけれど、畑にあった種は生き生きと育ってゆく。
9月の終わりに青々としたサヤをつけていたあずきは、ひと月で茶に変わり、収穫の時期を迎える。収穫したサヤからは輝くようなあずきがこぼれ落ちる。赤い粒たちはまるで尊い宝のように輝く。見慣れているはずなのにきらきらと輝く一粒一粒に感動してしまう。

ぬくもりの香り
工房では明子さんがあんこを作る。普通のあずきよりひと回り大きいのが特徴の柳田さんのあずき。水分をたっぷり吸って大きく膨らんだあずきに砂糖を加え、焦げ付かないよう注意深く炊いていく。自然の甘み。炊きたてのあずきのにおいを間近に感じる。餡を炊く力作業を気づかい、隆雄さんが「気をつけろよ」と声をかける姿が印象的だ。くつくつとあたたまり、甘くやさしいあんこが完成した。
「この地で作る丹波大納言あずきを受け継いでいきたいけれど、どんな事も自分で築いたものでないと続けていけない。おしつけになってしまう。この地でしかできないあずき作りを理解し、築いていってくれることがこれからの願い」隆雄さんが口にする言葉の一つひとつからは、あずき作りに対する並々ならぬ情熱が、静かに伝わる。

熱い思いとやさしさが詰まった素朴なおはぎは格別。「あんこ」への安堵感は、作る人の姿を感じ取っていたからかもしれない。いよいよやってくる寒い冬を前に、小さなひと粒に思いを込める人たちの熱い心を感じることができた。茹であがったあずきの素朴なにおい。はじめてで、忘れられない温もりの香りだった。
SPECIAL THANKS
▶あずき工房やなぎた ホームページ